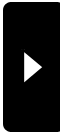2013年10月12日
改革への道筋 2、人づくり②後継者育成システム?
町の声を聞き集めた時によく出てくるママさん達から、よく聞く答え。
子連れで行ける場所(飲食店、お店)がない。雨の日に子どもが遊べる場所が欲しい。
図書館では、じっとできないし、騒げない。
もうひとつ、いろいろな場所で聞くのが、
後継者が育ちにくい環境。
これについては、農家、茶、陶器、大工、太鼓、祭り、、、ほぼすべての分野において聞くことがありました。
これをひっくるめて、解決できる策を考えたところ。
いろいろな職業や文化・伝統を体験できる無料の学習施設があれば、
子ども達にとっても、
親世代にとっても、
おじいちゃん世代にとっても楽しい施設になる可能性があります。
おいおい、ハコモノかよって思われるかもしれませんが、
最初は、公民館や地域市民センターでもいいと思います。
予算的に可能な時が来れば、作るかもしれない程度の話です。
市と市民の協働事業として行い、
幼少期から、いろいろなものに関心を持ってもらうのは、
子どもにとっては、一番大事なことです。
これは、いわゆる展示するだけのハコモノとは、訳が違います。
展示物は、一回見たら終わりですが、
体験することは、無限に広がっていきます。
またこれは、親子での体験ではなく、
知らない子ども同志での体験を目指します。
これは前述のつながる力を育むためにあります。
子どもが体験してる最中に、今度は親御さん向けの子育て相談や、
親御さん同士の交流も考えています。
正直に書きますが、今の親世代は、個人主義肯定派が多数を占めます。
個人主義は社会形成にとって、崩壊を導く一番大きな要素をはらんでいます。
これは対人関係が希薄になったり、限界集落を生み出したきっかけでもあります。
前項に記載しましたが、
人は一人では生きてはいけない。
一人で生きているわけではない。
必ず誰かに支えられて生きている。
そのことを認識している人が、実際には少ないんです。
自分がやりたい事だけをすればいいと言う人間だけでは、社会は絶対成り立ちません。
話を本題に戻しますが、
後継者育成により、これからこの町に残る若者を増やす機会になればいいと思ってます。
若者はどうしても、都会志向というか憧れを抱きますが、
いずれこの町に戻ってくる。
そんなシステム作りをしなければ、この町はいずれ高齢者だけの町になってしまいます。
それを阻止するためには、後継者支援の早い段階での導入が不可欠です。
子連れで行ける場所(飲食店、お店)がない。雨の日に子どもが遊べる場所が欲しい。
図書館では、じっとできないし、騒げない。
もうひとつ、いろいろな場所で聞くのが、
後継者が育ちにくい環境。
これについては、農家、茶、陶器、大工、太鼓、祭り、、、ほぼすべての分野において聞くことがありました。
これをひっくるめて、解決できる策を考えたところ。
いろいろな職業や文化・伝統を体験できる無料の学習施設があれば、
子ども達にとっても、
親世代にとっても、
おじいちゃん世代にとっても楽しい施設になる可能性があります。
おいおい、ハコモノかよって思われるかもしれませんが、
最初は、公民館や地域市民センターでもいいと思います。
予算的に可能な時が来れば、作るかもしれない程度の話です。
市と市民の協働事業として行い、
幼少期から、いろいろなものに関心を持ってもらうのは、
子どもにとっては、一番大事なことです。
これは、いわゆる展示するだけのハコモノとは、訳が違います。
展示物は、一回見たら終わりですが、
体験することは、無限に広がっていきます。
またこれは、親子での体験ではなく、
知らない子ども同志での体験を目指します。
これは前述のつながる力を育むためにあります。
子どもが体験してる最中に、今度は親御さん向けの子育て相談や、
親御さん同士の交流も考えています。
正直に書きますが、今の親世代は、個人主義肯定派が多数を占めます。
個人主義は社会形成にとって、崩壊を導く一番大きな要素をはらんでいます。
これは対人関係が希薄になったり、限界集落を生み出したきっかけでもあります。
前項に記載しましたが、
人は一人では生きてはいけない。
一人で生きているわけではない。
必ず誰かに支えられて生きている。
そのことを認識している人が、実際には少ないんです。
自分がやりたい事だけをすればいいと言う人間だけでは、社会は絶対成り立ちません。
話を本題に戻しますが、
後継者育成により、これからこの町に残る若者を増やす機会になればいいと思ってます。
若者はどうしても、都会志向というか憧れを抱きますが、
いずれこの町に戻ってくる。
そんなシステム作りをしなければ、この町はいずれ高齢者だけの町になってしまいます。
それを阻止するためには、後継者支援の早い段階での導入が不可欠です。
Posted by まえだのあっちゃん at 02:46│Comments(0)
│2013年版 町おこしに大切なもの